今日(11月16日)は、沖縄県の「イモの日」です。
「いいいむ(イモの方言)のひ」のゴロで11月16日だそうです。
沖縄では「イモ」と言えば、一般的にサツマイモのことを指しますから、つまりは「サツマイモの日」なのです。
というわけで、沖縄県での「イモ」と人々のかかわりをお話していきたいと思います。
歴史的に早く普及した「イモ」
沖縄県外では江戸時代の18世紀にサツマイモの栽培を普及しさせた青木昆陽が有名ですが、それ以前の17世紀の琉球ではイモの栽培が普及していたようです。
最も早くサツマイモを持ち込んだのは、宮古島の役人であった長真氏旨屋で、沖縄県本島では、野国総管がサツマイモを普及させたとされています。
大きな河川や、その下流に広がる平野部などがない沖縄では、コメの栽培に適した土地は限られています。
さらに、台風や干ばつなどの災害に強く、温暖な気候もあって、サツマイモの栽培は瞬く間に広がったというのは想像に難くありません。
当時もサツマイモが普及したおかげで、多くの人々が飢餓から救われたこととは思うのですが、それは第二次世界大戦後の沖縄でも同様でした。
戦後の食糧難を救った「イモ」
今でも60代後半以上の年齢の方々から話を聞くと、子供の頃によく「イモ」を食べていたという話を聞きます。
聞いてる限りでは、戦後の食糧難の時代のイモは、少なくとも農村部では主食だったのだと思います。
当時は主食としてイモを栽培しているだけでなく、家畜用のエサや、葉を野菜としても利用していたようですし、換金作物としても利用していたようです。
例えばある先輩農家(70代 八重瀬町)のお話によると、
子供の頃は一番良いイモは糸満や那覇の市場に売りに行って、その次に良い物を蒸かして、カンダバー(イモの葉っぱ)の味噌汁と食べて、それ以下のイモやカズラ(イモの葉っぱや茎)はシーメー鍋(直径1mほどもある大きな鍋)で煮て、豚のエサにしていた。
なんていうことが日常だったようです。
さらに、イモをすりおろして水にさらして澱粉を取り、その搾りかすを線香の原料として売っていた、なんて話も聞かせてもらいました。
「イモ」と「ゆし豆腐」
「毎日イモを食べていた」「コメはごちそうだった」
こんな話の後、2つの派に分かれます、
「あの時のイモは美味かった」「食べ過ぎてもう食べたくない」
しかし、どちらの派にも一致することが多いのは、
「蒸かしイモとゆし豆腐の組み合わせは最高!」
ということです。
「ゆし豆腐」とは、豆乳ににがりを加えただけの状態の、半分固まった豆腐がふわふわしている、豆腐を固める前のものに、カツオだしや塩を加えて味を調えた汁物です。
試したことがない方は、ぜひ経験してもらいたいです。
個人的には、「ご飯に味噌汁」「ビールに枝豆」「イモにゆし豆腐」だと思っています。
なお、この場合はねっとりとした甘みの強いサツマイモではなくて、ホクホクとした、やや粉質の、甘さ控えめな品種のサツマイモが合うと思います。
あくまで「個人的には」ですよ。
現在の沖縄の「イモ」
かつては主食や家畜のエサとして重要だったイモの栽培も、食糧難の時代が去り、人々の生活が豊かになるにつれて減少していきました。
そのような中で、「紅いもタルト」の誕生は、沖縄のイモ栽培に大きな転機でした。
1,986年に誕生したお菓子「紅いもタルト」は、その後沖縄県内の複数の会社で製造されるようになり、お土産品として不動の地位を築くに至ります。
それとともに、沖縄のイモの栽培も復活の兆しを見せました。
その結果、現在の沖縄ではお土産品の「紅いもタルト」の原料としての流通が主流となっています。
また、沖縄といえば紅いも、というイメージが定着すると、「紅いもタルト」以外の商品も開発されるようになってきています。

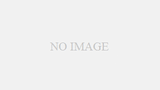
コメント